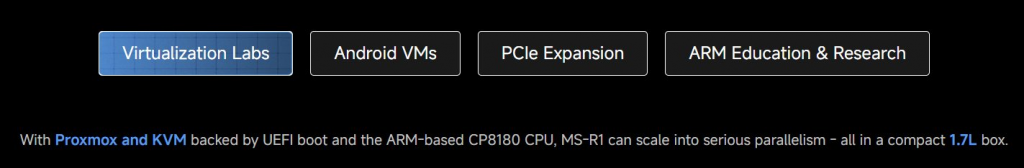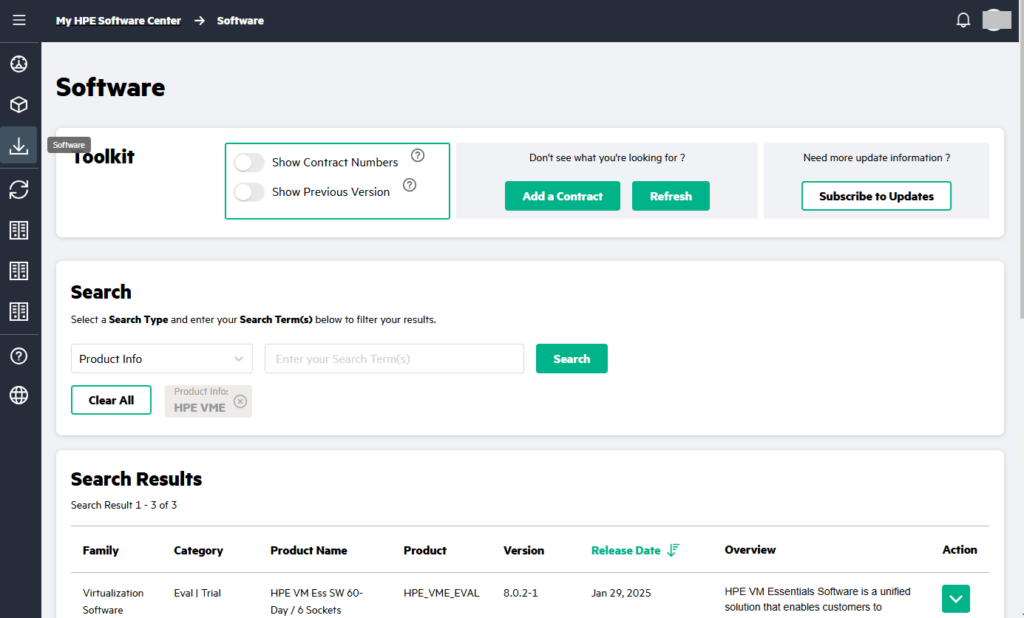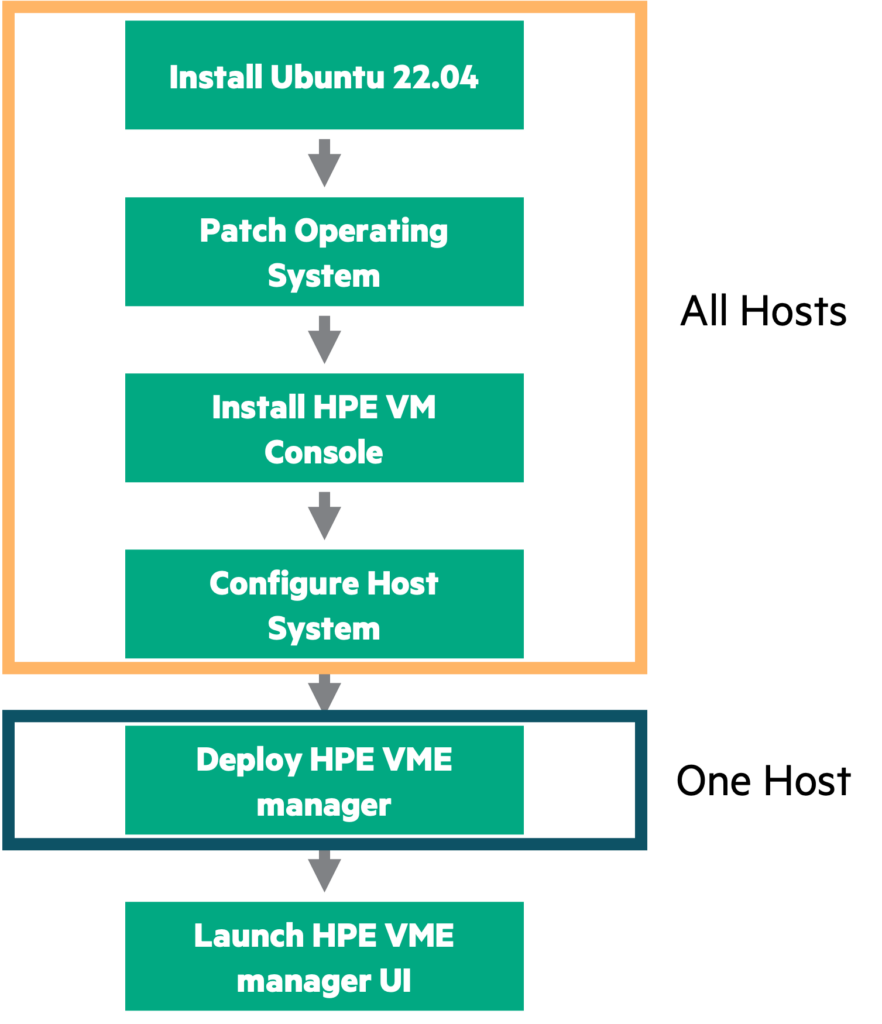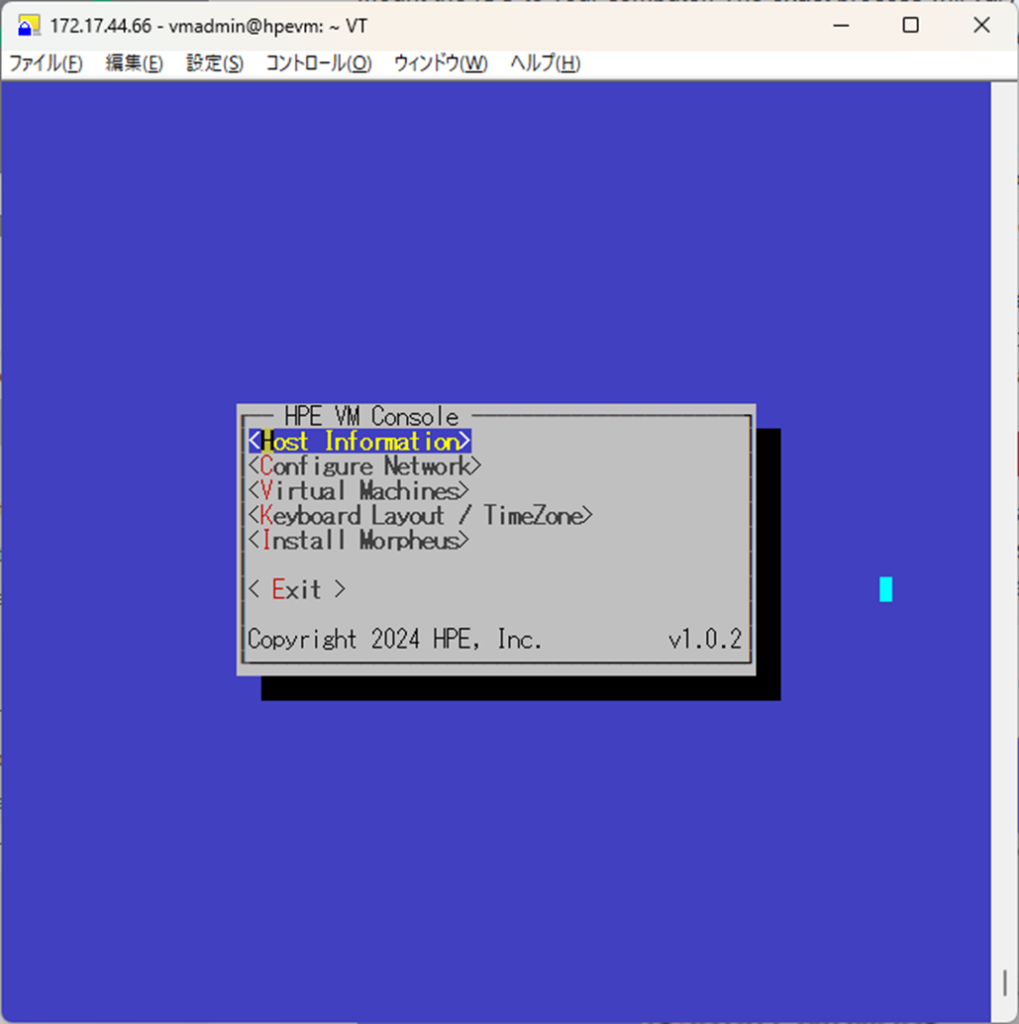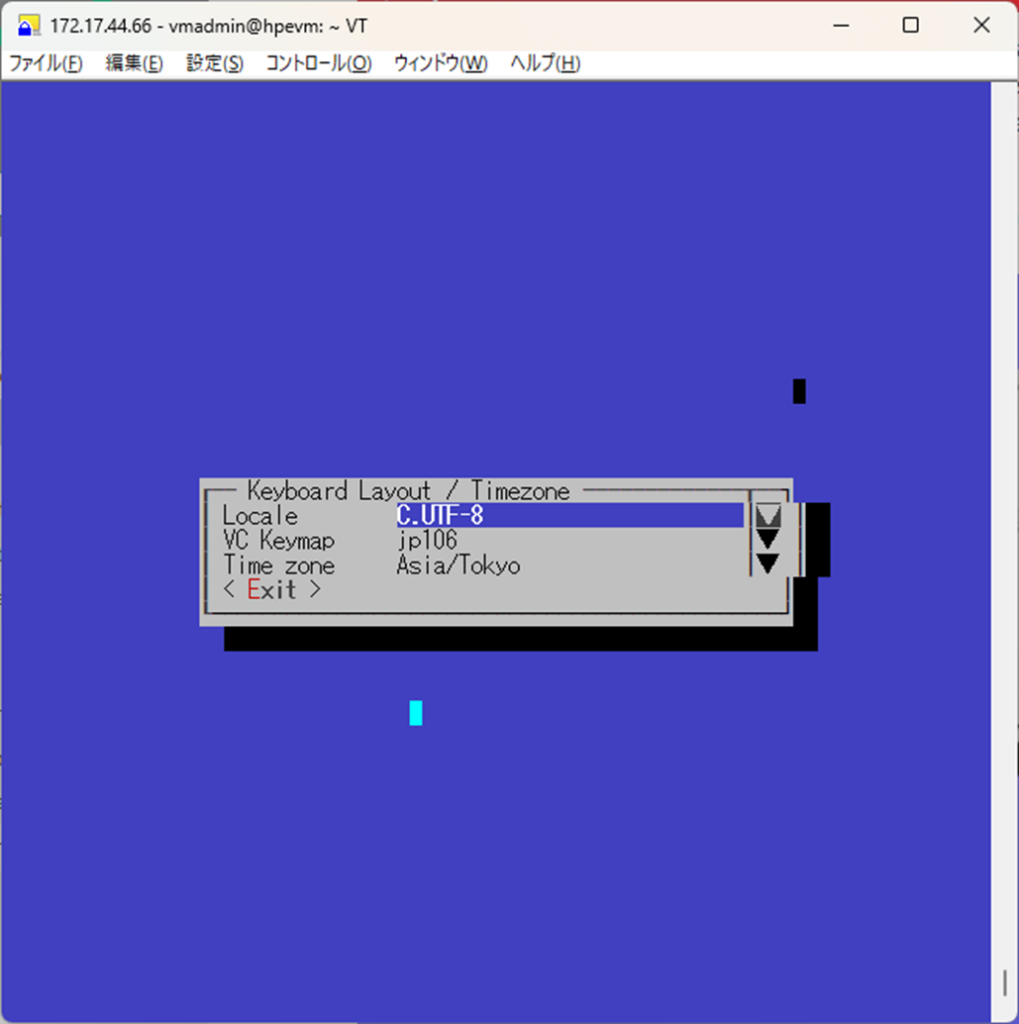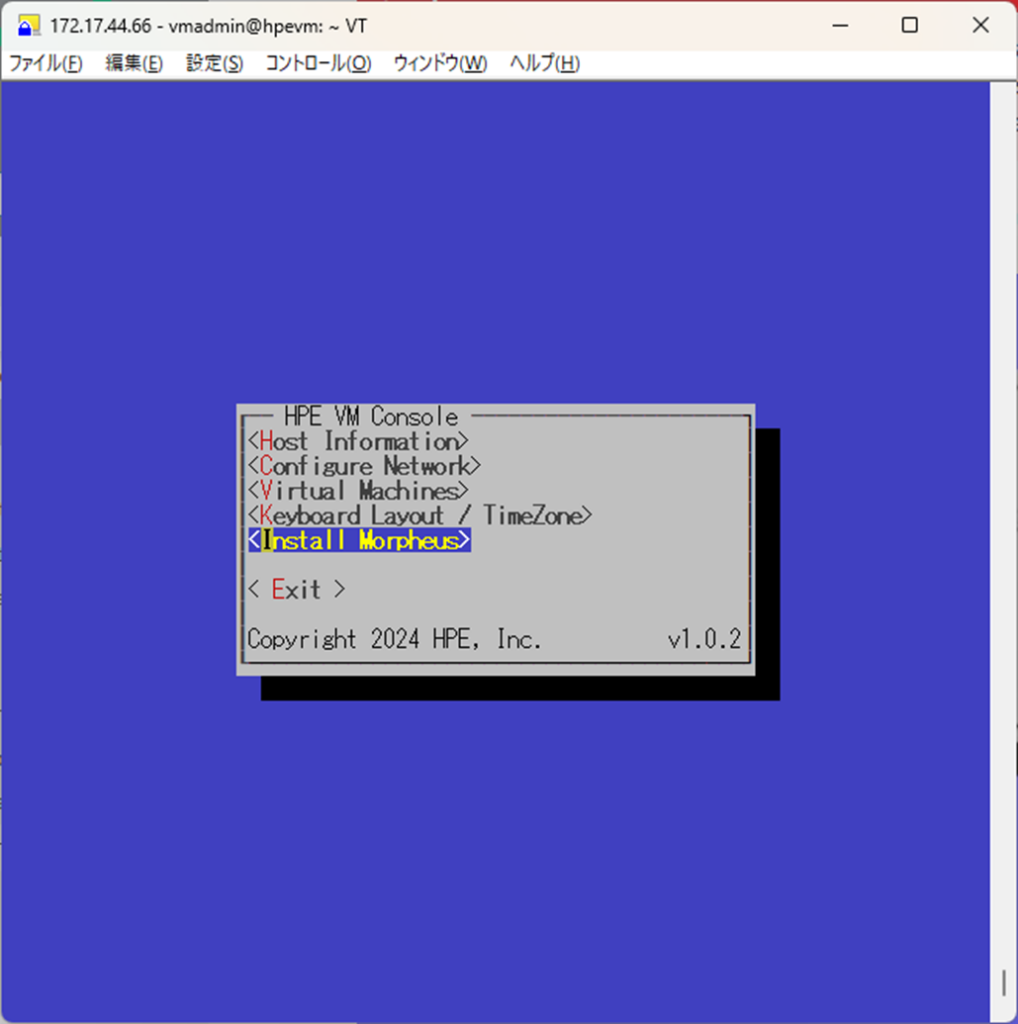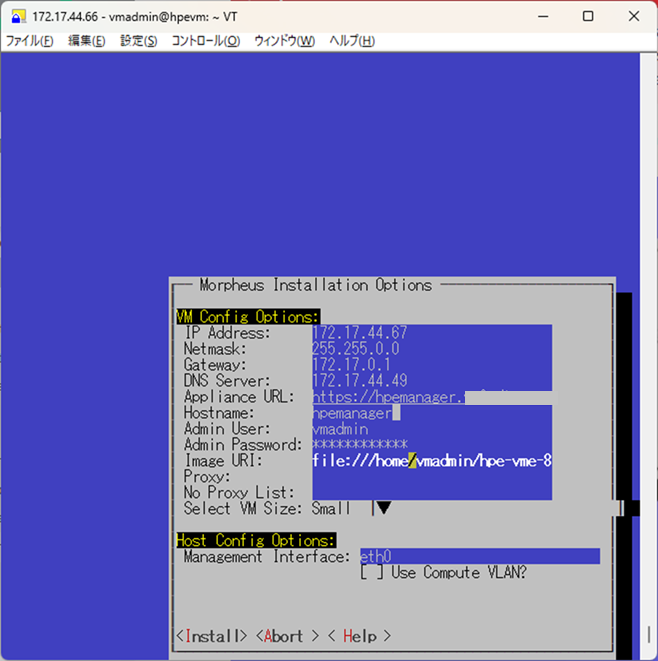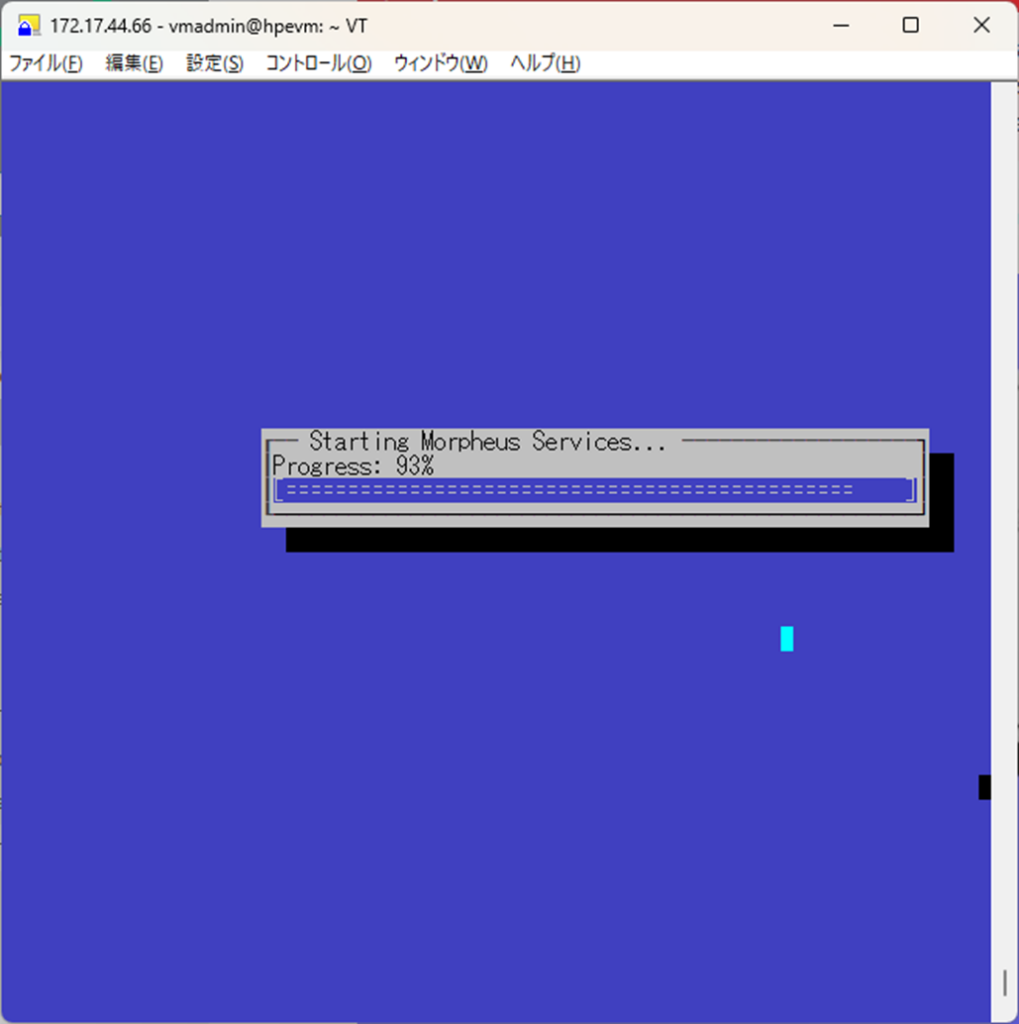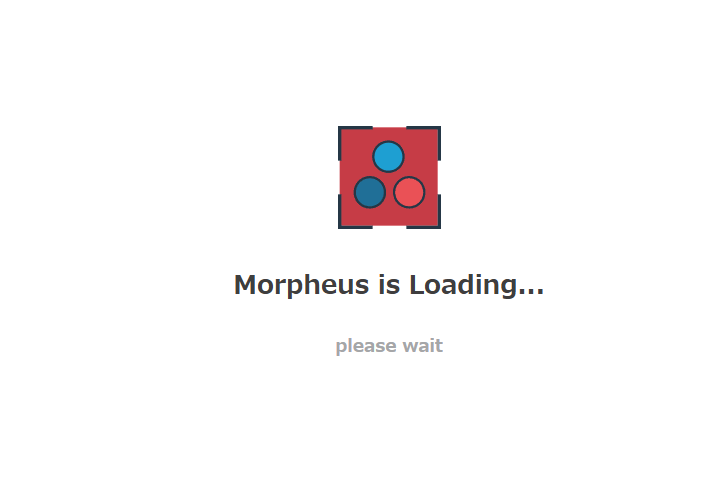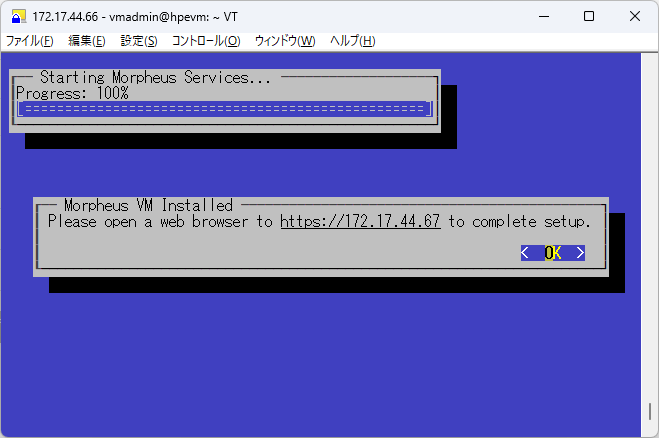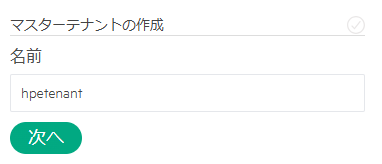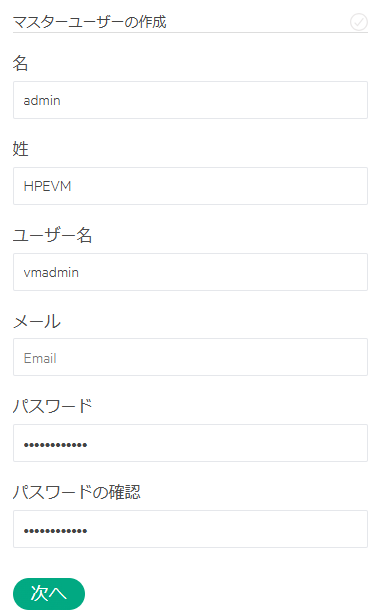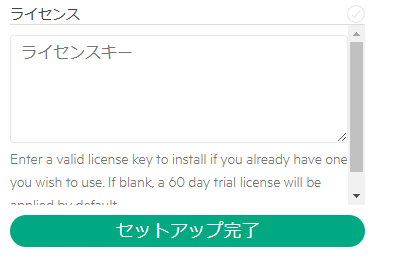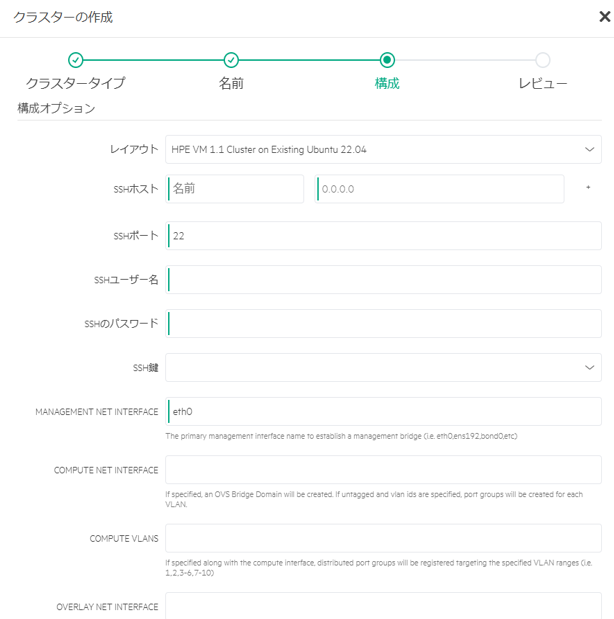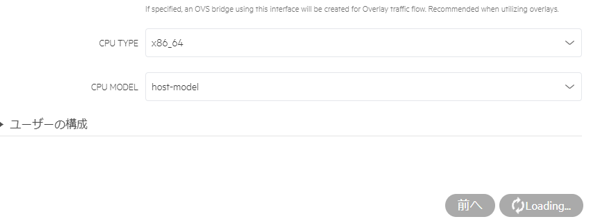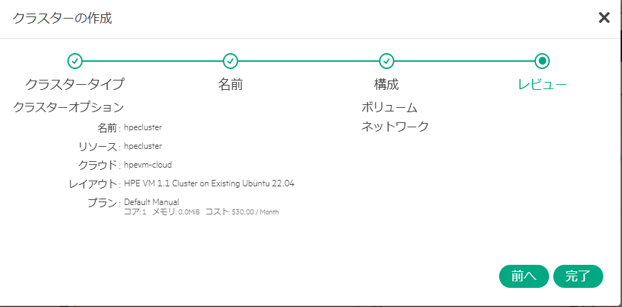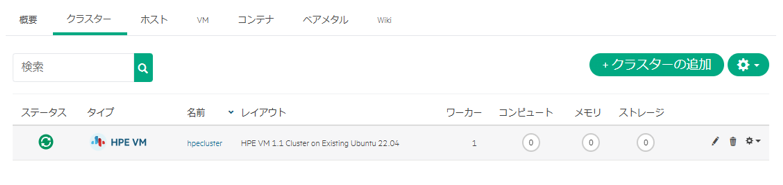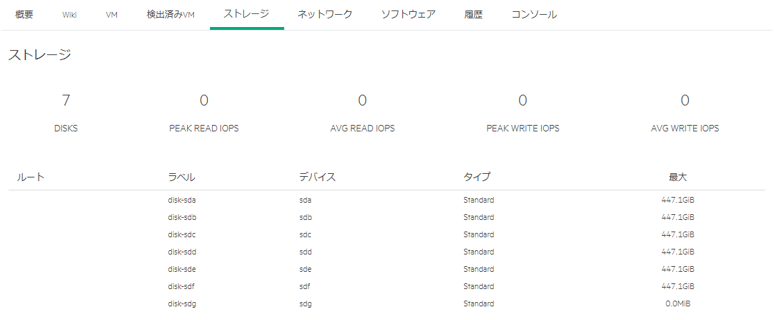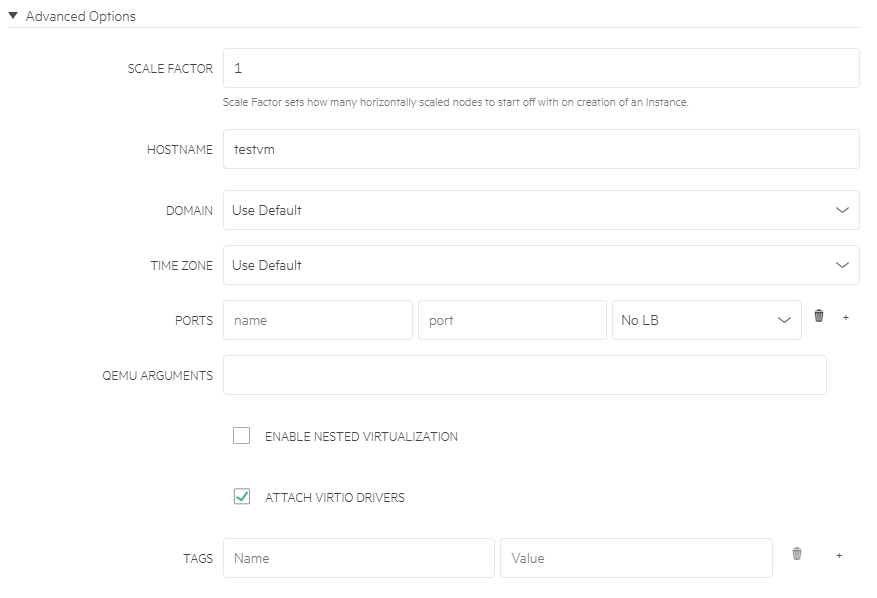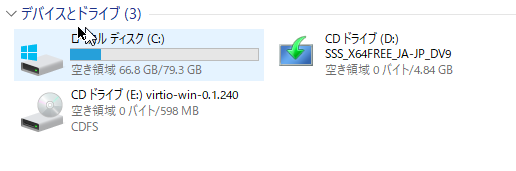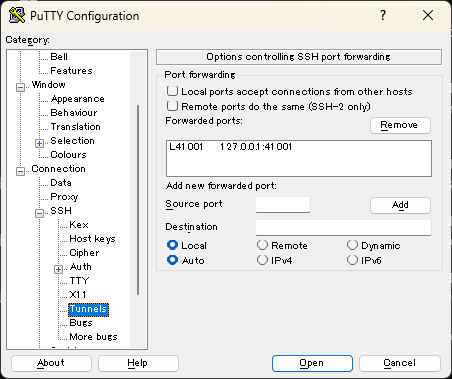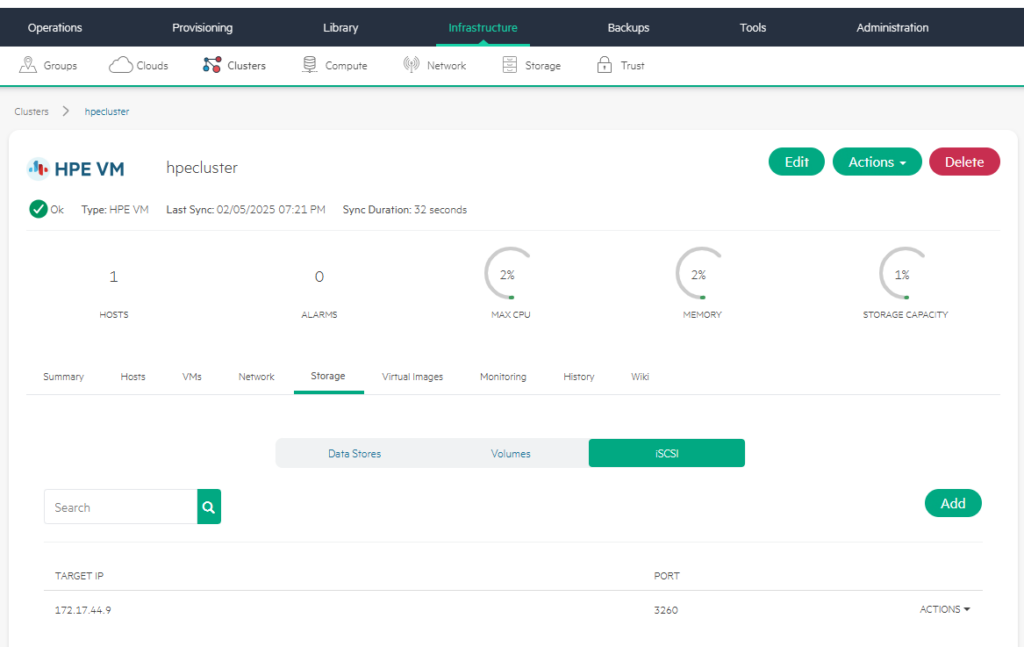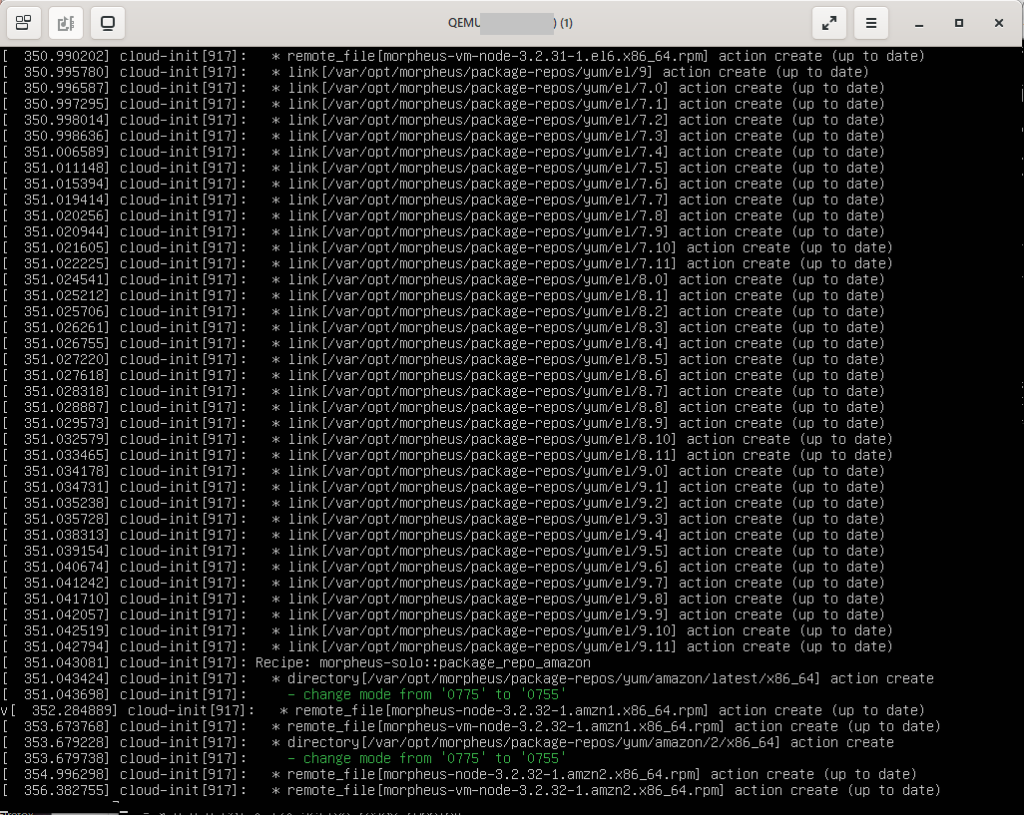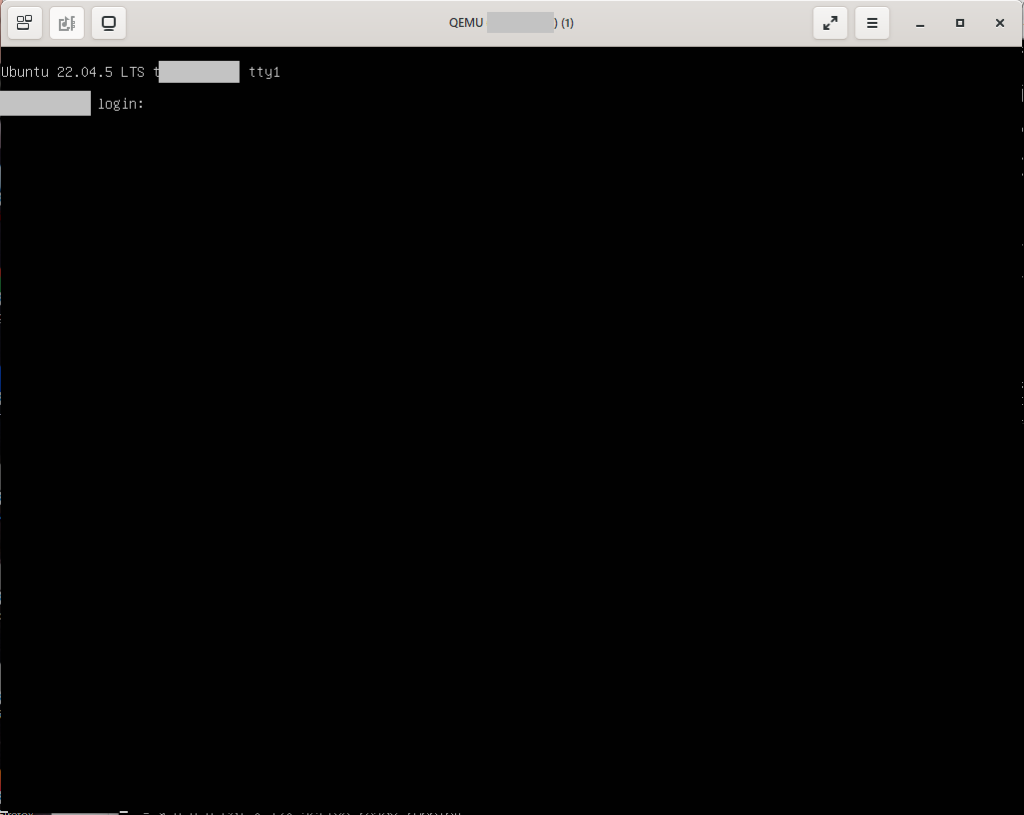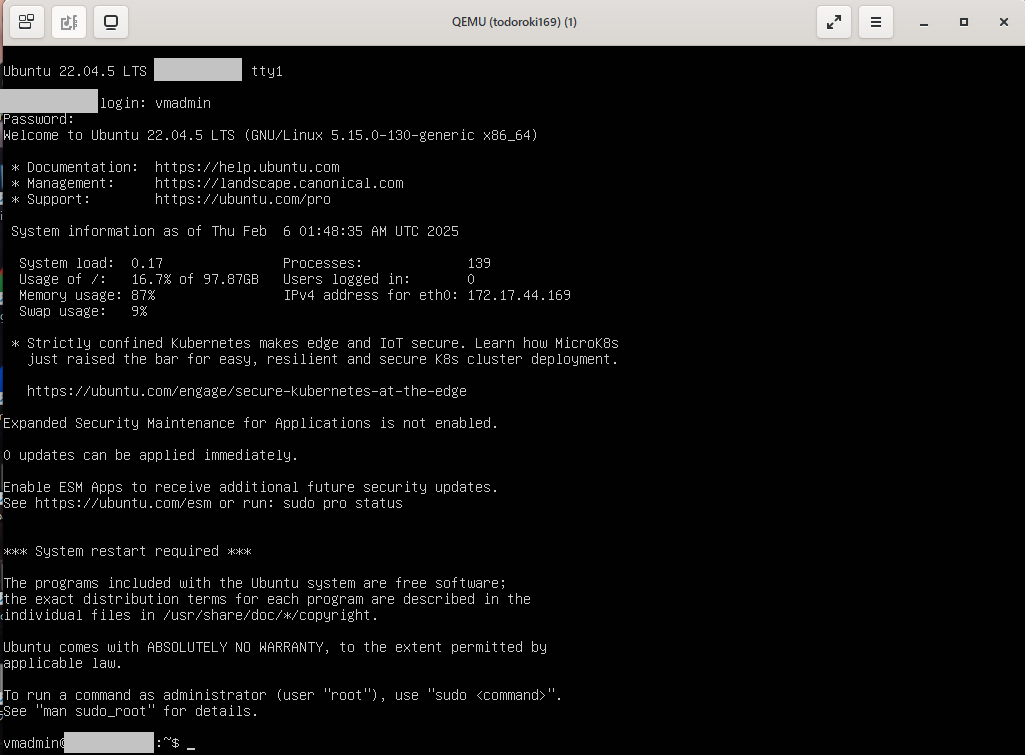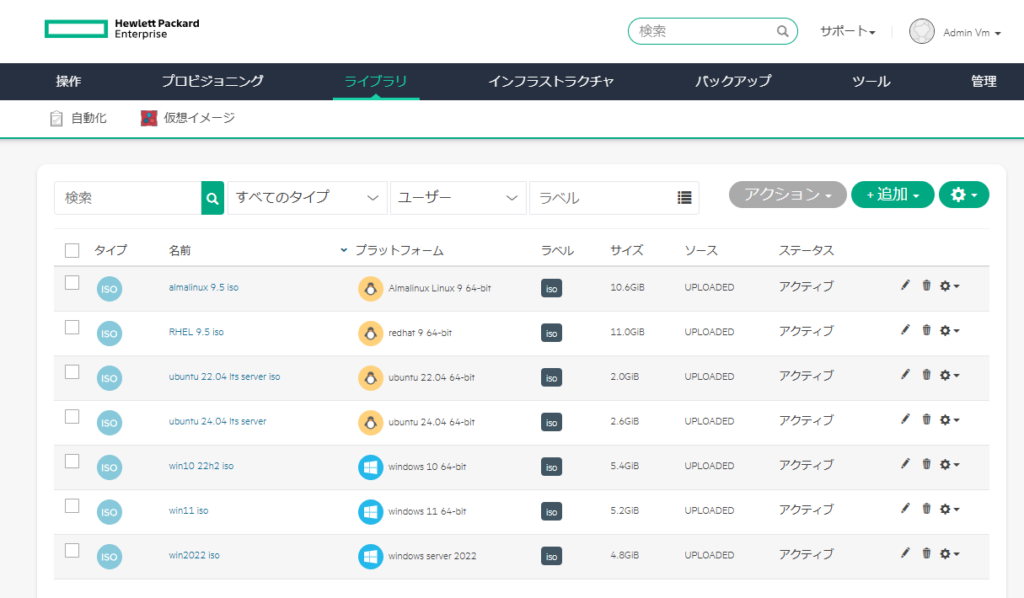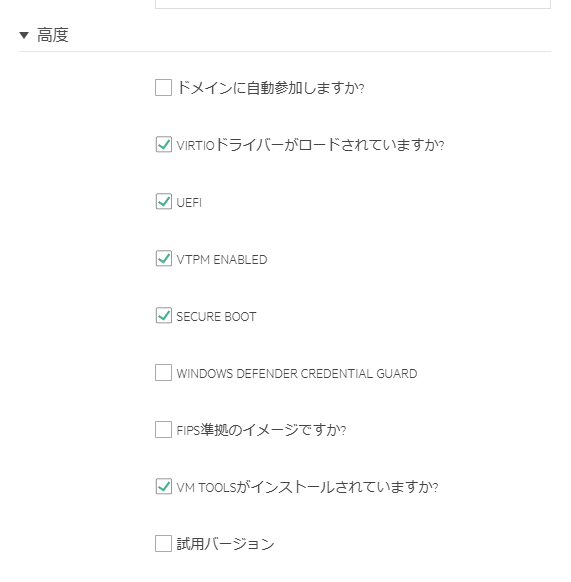Ryzen 5 3500U搭載GMKtec G10 mini上に構築した vSphere ESXi 8.0 Freeの検証環境にて、Proxmox VE 9.1仮想マシン3台構成でクラスタを作成し、HA試験を行ったところ、3台中1台に対して失敗した。
結果を先に書いておくと、Proxmox VE環境上の仮想マシン挙動で発覚したが、実際の問題はvSphre ESXiの仮想CPUの作りの問題でした。
さて、発覚した状況としては、Proxmox VE上でHA設定をしている場合、仮想マシンを動かしていたサーバを停止すると、稼働中のサーバ上で再起動してくるはずが、下記のエラーで起動が失敗していた。
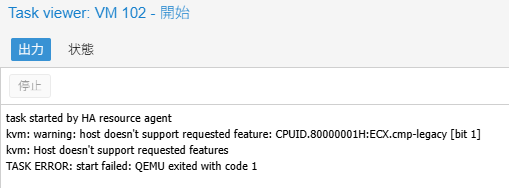
task started by HA resource agent
kvm: warning: host doesn't support requested feature: CPUID.80000001H:ECX.cmp-legacy [bit 1]
kvm: Host doesn't support requested features
TASK ERROR: start failed: QEMU exited with code 1
3台とも仮想マシンの4vCPUにしてるはずなんだけど・・・と思ってCPU設定を見直してみると、ソケット数が違っていた
proxmox1, proxmox2は1ソケット4コア
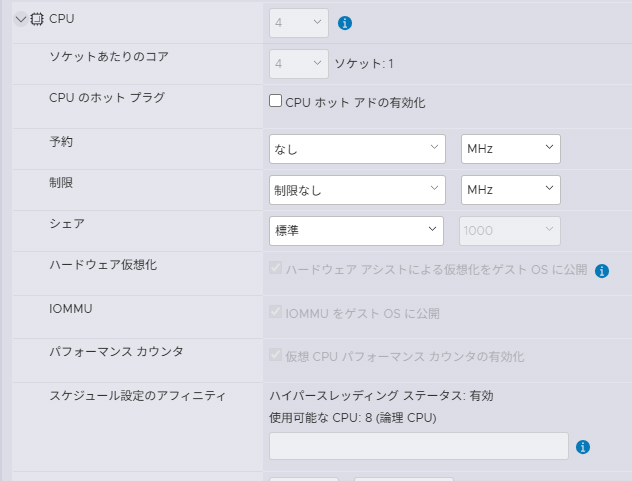
proxmox3は4ソケット1コア
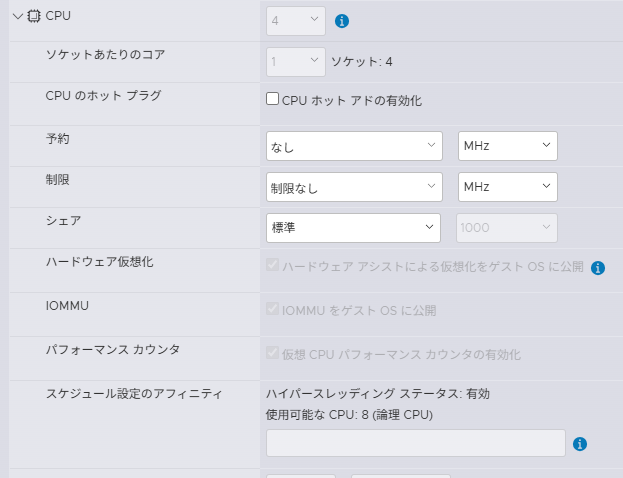
この影響なのか、/proc/cpuinfoに違いが・・・
proxmox1とproxmox2の/proc/cpuinfo
root@proxmox2:~# ssh proxmox1 cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 4
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 2
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 2
cpu cores : 4
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 3
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 3
cpu cores : 4
apicid : 3
initial apicid : 3
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
root@proxmox2:~#
proxmox3の/proc/cpuinfo
root@proxmox2:~#
ssh proxmox3 cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 2
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 2
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 4
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 4
initial apicid : 4
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 3
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 6
siblings : 1
core id : 0
cpu cores : 1
apicid : 6
initial apicid : 6
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
root@proxmox2:~#
proxmox3のflagsには「ht」「cmp_legacy」がない。
またproxmox3のbugsには「spectre_v2_user」がある
proxmox3は1つのCPU内に複数のコア/スレッドがないので、hyper thread機能が存在しない、ということで消されていた模様
このため、proxmox3仮想マシンを一度停止し、CPU設定を1ソケット4コアに揃えたところ、flagsに「ht」と「cmp_legacy」が追加されたことを確認した
root@proxmox2:~# ssh proxmox3 cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 4
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 2
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 2
cpu cores : 4
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 3
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 23
model : 24
model name : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping : 1
microcode : 0x8108109
cpu MHz : 2100.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 3
cpu cores : 4
apicid : 3
initial apicid : 3
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero arat npt svm_lock nrip_save vmcb_clean flushbyasid decodeassists overflow_recov succor
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips : 4200.00
TLB size : 2560 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:
root@proxmox2:~#
というわけで、vSphere ESXi 8.0上で「4vCPU」を設定する場合、「1CPU 4コア設定」と「4CPU1コア設定」とで提供されるCPU機能が異なり、一部の挙動が変わる、ということでした。