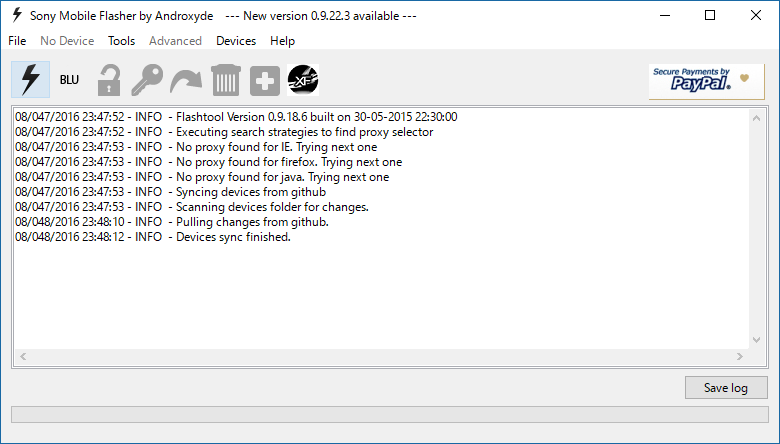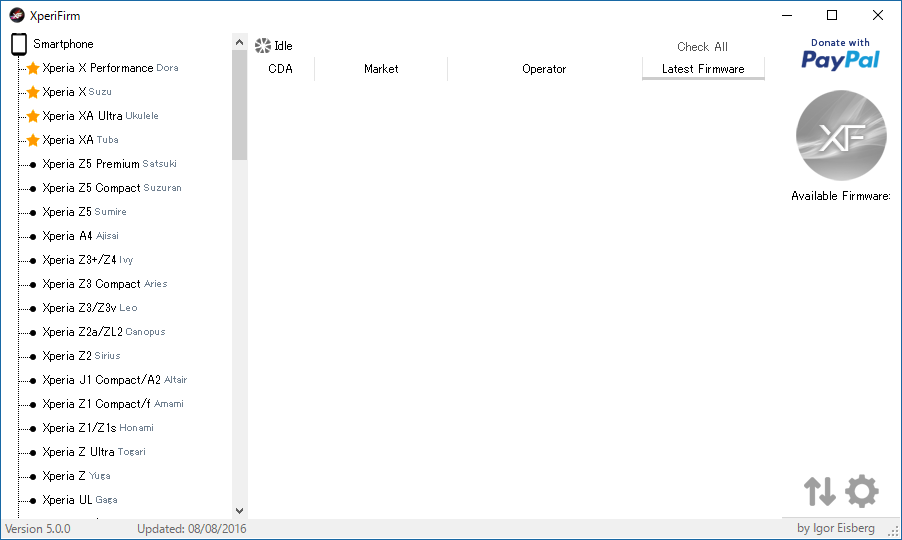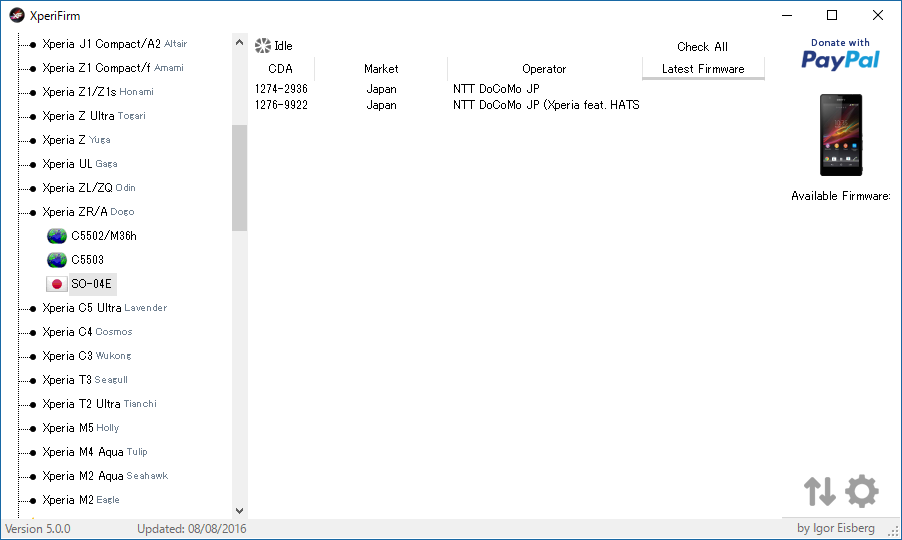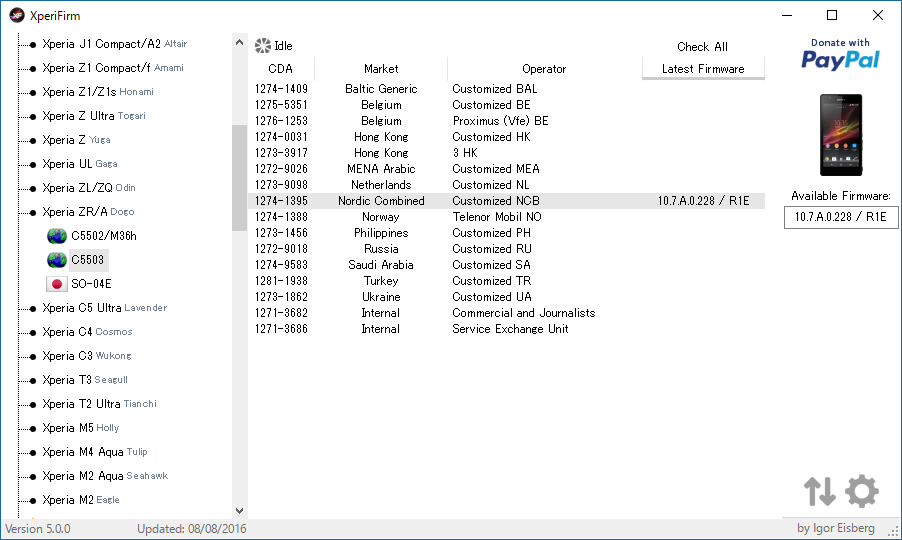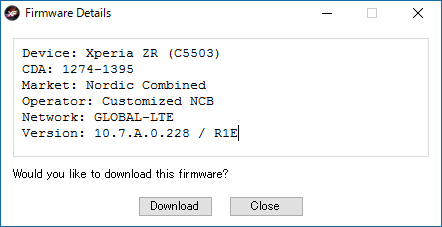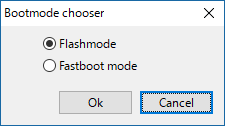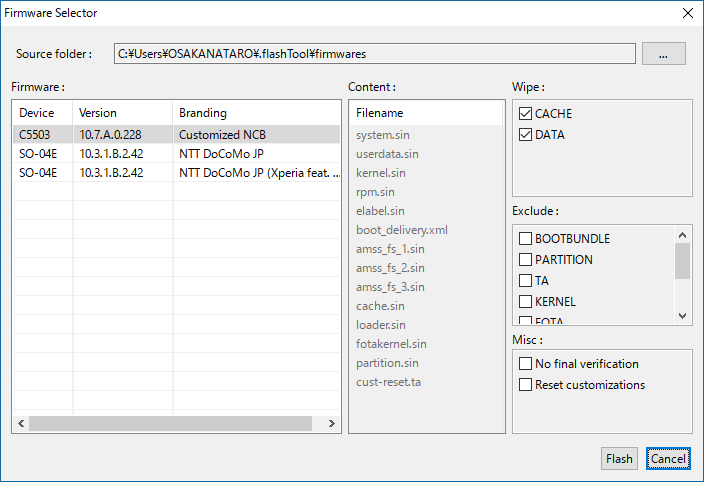前はMegaCliだったものが、いまは違うらしい。
中古で手に入れたサーバにMegaRAID SAS 8708EM2が入ってたので必要になったので確認してみた。
(2017/03/02追記:firmwareアップデート手順として「storcliを使ってMegaSASのfirmwareをアップデートする手順」を公開しています)
Avagoの「Support Documents and Downloads」から「Product Family:Legacy RAID Controllers」の「Product:MegaRAID SAS 8708EM2」を選択し、検索。
Broadcomの「SUPPORT DOCUMENTS AND DOWNLOADS」からProduct Familyの下の方にあるLegacy Product群から「Product Family:Legacy RAID Controllers」を選択肢、検索。
「Management Software and Tools」にあるが、なぜか「Current」には出てこないので「Archive」を選択。
「Binary」の「Currect」もしくは「Archive」に管理ソフトがある。
もしくは「storcliの検索結果」から「Management Software and Tools」からダウンロードする。
「MegaRAID Storage Manager (MSM)」はJavaで動くGUIツール。
「StorCLI」もしくは「MegaRAID StorCLI」は、コマンドのみ
「MegaRAID Storage Manager (MSM)」の最新版はMR6.9なのに、StorCLIはMR6.8が最新なのはなぜなのか・・・
rpmからインストールすると、/opt/MegaRAID以下にインストールされる。
実行ファイルは、/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 か /opt/MegaRAID/storcli/storcli。
まずは、コントローラのリストを「storcli64 show」で取得
# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 show
Status Code = 0
Status = Success
Description = None
Number of Controllers = 1
Host Name = example.osakana.net
Operating System = Linux3.10.0-327.28.2.el7.x86_64
System Overview :
===============
------------------------------------------------------------------------------
Ctl Model Ports PDs DGs DNOpt VDs VNOpt BBU sPR DS EHS ASOs Hlth
------------------------------------------------------------------------------
0 MegaRAIDSAS8708EM2 8 3 1 0 1 0 Opt On 2 N 0 Opt
------------------------------------------------------------------------------
Ctl=Controller Index|DGs=Drive groups|VDs=Virtual drives|Fld=Failed
PDs=Physical drives|DNOpt=DG NotOptimal|VNOpt=VD NotOptimal|Opt=Optimal
Msng=Missing|Dgd=Degraded|NdAtn=Need Attention|Unkwn=Unknown
sPR=Scheduled Patrol Read|DS=DimmerSwitch|EHS=Emergency Hot Spare
Y=Yes|N=No|ASOs=Advanced Software Options|BBU=Battery backup unit
Hlth=Health|Safe=Safe-mode boot
#
コントローラの番号が判明したので「storcli64 /c0 show」と、コントローラを指定して、詳細を確認。
# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show
Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2
Serial Number = P322610710
SAS Address = 500605b001eedcb0
PCI Address = 00:01:00:00
System Time = 08/10/2016 17:24:17
Mfg. Date = 02/24/10
Controller Time = 08/10/2016 08:24:13
FW Package Build = 11.0.1-0008
FW Version = 1.40.32-0580
BIOS Version = 2.06.00
Driver Name = megaraid_sas
Driver Version = 06.807.10.00-rh1
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0x60
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x1013
Host Interface = PCI-E
Device Interface = SAS-3G
Bus Number = 1
Device Number = 0
Function Number = 0
Drive Groups = 1
TOPOLOGY :
========
--------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace
--------------------------------------------------------------------------
0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N
0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N
0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -
0 0 1 252:1 1 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -
--------------------------------------------------------------------------
DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID
DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded
Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active
PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign
DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present
Virtual Drives = 1
VD LIST :
=======
-----------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name
-----------------------------------------------------------
0/0 RAID1 Optl RW No NRWBD - 135.937 GB
-----------------------------------------------------------
Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded
Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|
R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
Physical Drives = 3
PD LIST :
=======
-------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
-------------------------------------------------------------------------
252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U
252:1 1 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U
252:2 2 GHS - 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U
-------------------------------------------------------------------------
EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup
DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare
UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface
Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info
SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign
UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded
CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded
BBU_Info :
========
------------------------------------------------------------
Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn
------------------------------------------------------------
iBBU Optimal N/A 37C - 2010/05/14 None
------------------------------------------------------------
#
146GB SAS HDDが3本認識されていて
RAID1で2本、スペアで1本使われている。
バッテリーバックアップユニット(BBU)が入ってるので、ステータスを「storcli64 /c0 /bbu show all」で確認する。
# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /bbu show all
Controller = 0
Status = Success
Description = None
BBU_Info :
========
----------------------
Property Value
----------------------
Type iBBU
Voltage 4069 mV
Current 0 mA
Temperature 37 C
Battery State Optimal
----------------------
BBU_Firmware_Status :
===================
-------------------------------------------------
Property Value
-------------------------------------------------
Charging Status None
Voltage OK
Temperature OK
Learn Cycle Requested No
Learn Cycle Active No
Learn Cycle Status OK
Learn Cycle Timeout No
I2C Errors Detected No
Battery Pack Missing No
Replacement required No
Remaining Capacity Low No
Periodic Learn Required No
Transparent Learn No
No space to cache offload No
Pack is about to fail & should be replaced No
Cache Offload premium feature required No
Module microcode update required No
-------------------------------------------------
GasGaugeStatus :
==============
---------------------------------
Property Value
---------------------------------
Fully Discharged No
Fully Charged Yes
Discharging Yes
Initialized Yes
Remaining Time Alarm No
Remaining Capacity Alarm No
Terminate Discharge Alarm No
Over Temperature No
Charging Terminated No
Over Charged No
Relative State of Charge 100%
Charger System State 49168
Charger System Ctrl 0
Charging current 0 mA
Absolute state of charge 98%
Max Error 2%
Battery backup charge time N/A
---------------------------------
BBU_Capacity_Info :
=================
------------------------------------------------------
Property Value
------------------------------------------------------
Relative State of Charge 100%
Absolute State of charge 98%
Remaining Capacity 663 mAh
Full Charge Capacity 665 mAh
Run time to empty Battery is not being charged
Average time to empty Battery is not being charged
Average Time to full Battery is not being charged
Cycle Count 96
Max Error 2%
Remaining Capacity Alarm 70 mAh
Remining Time Alarm 10 minutes(s)
------------------------------------------------------
BBU_Design_Info :
===============
-----------------------------------
Property Value
-----------------------------------
Date of Manufacture 14/05/2010
Design Capacity 675 mAh
Design Voltage 3700 mV
Specification Info 33
Serial Number 4643
Pack Stat Configuration 6490
Manufacture Name LS1113001A
Device Name 2970701
Device Chemistry LION
Battery FRU N/A
Transparent Learn 0
App Data 0
-----------------------------------
BBU_Properties :
==============
-------------------------------------------
Property Value
-------------------------------------------
Auto Learn Period 30d (2592000 seconds)
Next Learn time None
Learn Delay Interval 0 hour(s)
Auto-Learn Mode Disabled
-------------------------------------------
#
どうやら、まだ生きている模様。
・・・最初は死んでたんだけど「storcli64 /c0 /bbu start learn」とBBUの状態調査を行わせてしばらく放置したら生き返った感じで・・・
2023/05/18 追記
久々にコマンドたたいてみたらディスクが1本死んでいた
-bash-4.2$ sudo /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call show
Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2
Serial Number = P322610710
SAS Address = 500605b001eedcb0
PCI Address = 00:01:00:00
System Time = 05/18/2023 18:19:42
Mfg. Date = 02/24/10
Controller Time = 05/18/2023 09:04:58
FW Package Build = 11.0.1-0048
FW Version = 1.40.342-1650
BIOS Version = 2.07.00
Driver Name = megaraid_sas
Driver Version = 07.714.04.00-rh1
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0x60
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x1013
Host Interface = PCI-E
Device Interface = SAS-3G
Bus Number = 1
Device Number = 0
Function Number = 0
Drive Groups = 1
TOPOLOGY :
========
--------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace
--------------------------------------------------------------------------
0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N
0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N
0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -
0 0 1 252:2 2 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -
--------------------------------------------------------------------------
DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID
DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded
Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active
PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign
DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present
Virtual Drives = 1
VD LIST :
=======
-----------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name
-----------------------------------------------------------
0/0 RAID1 Optl RW Yes NRWBD - 135.937 GB
-----------------------------------------------------------
Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded
Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|
R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
Physical Drives = 3
PD LIST :
=======
-------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
-------------------------------------------------------------------------
252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U
252:1 1 UBad F 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U
252:2 2 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U
-------------------------------------------------------------------------
EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup
DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare
UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface
Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info
SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign
UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded
CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded
BBU_Info :
========
--------------------------------------------------------------------------
Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn
--------------------------------------------------------------------------
iBBU Dgd (Needs Attention) N/A 39C - 2010/05/14 None
--------------------------------------------------------------------------
-bash-4.2$ sudo /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call /pall show
Controller = 0
Status = Success
Description = None
PhyInfo :
=======
----------------------------------------------------------------------------
PhyNo SAS_Addr Phy_Identifier Link_Speed Device_Type Description
----------------------------------------------------------------------------
0 0x500000E114F453F2 0 No limit End Device -
1 0x500000E119865C22 0 No limit End Device -
2 0x5000CCA00A335A55 0 No limit End Device -
3 0x0000000000000000 0 No limit - -
4 0x0000000000000000 0 No limit - -
5 0x0000000000000000 0 No limit - -
6 0x0000000000000000 0 No limit - -
7 0x0000000000000000 0 No limit - -
----------------------------------------------------------------------------
-bash-4.2$ sudo /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call /vall show
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Virtual Drives :
==============
-----------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name
-----------------------------------------------------------
0/0 RAID1 Optl RW Yes NRWBD - 135.937 GB
-----------------------------------------------------------
Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded
Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|
R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
-bash-4.2$
2024/08/27追記
ディスクが壊れたので交換した。
ただ、300GB SASのST300MM0048を用意したのだが、なぜか認識しなかったので、予備として持って行ったSATAディスクをつけている。
これでほんとにスペアとして動いてくれるのかは未検証である
# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call show
Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2
Serial Number = P322610710
SAS Address = 500605b001eedcb0
PCI Address = 00:01:00:00
System Time = 08/27/2024 09:58:50
Mfg. Date = 02/24/10
Controller Time = 08/27/2024 00:58:36
FW Package Build = 11.0.1-0048
FW Version = 1.40.342-1650
BIOS Version = 2.07.00
Driver Name = megaraid_sas
Driver Version = 07.714.04.00-rh1
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0x60
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x1013
Host Interface = PCI-E
Device Interface = SAS-3G
Bus Number = 1
Device Number = 0
Function Number = 0
Drive Groups = 1
TOPOLOGY :
========
--------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace
--------------------------------------------------------------------------
0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N
0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N
0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -
0 0 1 252:2 2 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -
--------------------------------------------------------------------------
DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID
DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded
Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active
PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign
DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present
Virtual Drives = 1
VD LIST :
=======
-----------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name
-----------------------------------------------------------
0/0 RAID1 Optl RW Yes NRWTD - 135.937 GB
-----------------------------------------------------------
Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded
Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|
R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
Physical Drives = 3
PD LIST :
=======
--------------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
--------------------------------------------------------------------------------
252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U
252:1 1 UGood - 297.562 GB SATA HDD N N 512B Hitachi HTS725032A9A364 U
252:2 2 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U
--------------------------------------------------------------------------------
EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup
DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare
UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface
Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info
SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign
UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded
CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded
BBU_Info :
========
--------------------------------------------------------------------------
Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn
--------------------------------------------------------------------------
iBBU Dgd (Needs Attention) N/A 36C - 2010/05/14 None
--------------------------------------------------------------------------
# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0/e252/s1 add hotsparedrive
Controller = 0
Status = Success
Description = Add Hot Spare Succeeded.
# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call show
Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2
Serial Number = P322610710
SAS Address = 500605b001eedcb0
PCI Address = 00:01:00:00
System Time = 08/27/2024 10:01:04
Mfg. Date = 02/24/10
Controller Time = 08/27/2024 01:00:50
FW Package Build = 11.0.1-0048
FW Version = 1.40.342-1650
BIOS Version = 2.07.00
Driver Name = megaraid_sas
Driver Version = 07.714.04.00-rh1
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0x60
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x1013
Host Interface = PCI-E
Device Interface = SAS-3G
Bus Number = 1
Device Number = 0
Function Number = 0
Drive Groups = 1
TOPOLOGY :
========
--------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace
--------------------------------------------------------------------------
0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N
0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N
0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -
0 0 1 252:2 2 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -
--------------------------------------------------------------------------
DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID
DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded
Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active
PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign
DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present
Virtual Drives = 1
VD LIST :
=======
-----------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name
-----------------------------------------------------------
0/0 RAID1 Optl RW Yes NRWTD - 135.937 GB
-----------------------------------------------------------
Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded
Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|
R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
Physical Drives = 3
PD LIST :
=======
--------------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
--------------------------------------------------------------------------------
252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U
252:1 1 GHS - 297.562 GB SATA HDD N N 512B Hitachi HTS725032A9A364 U
252:2 2 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U
--------------------------------------------------------------------------------
EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup
DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare
UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface
Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info
SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign
UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded
CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded
BBU_Info :
========
--------------------------------------------------------------------------
Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn
--------------------------------------------------------------------------
iBBU Dgd (Needs Attention) N/A 36C - 2010/05/14 None
--------------------------------------------------------------------------
#